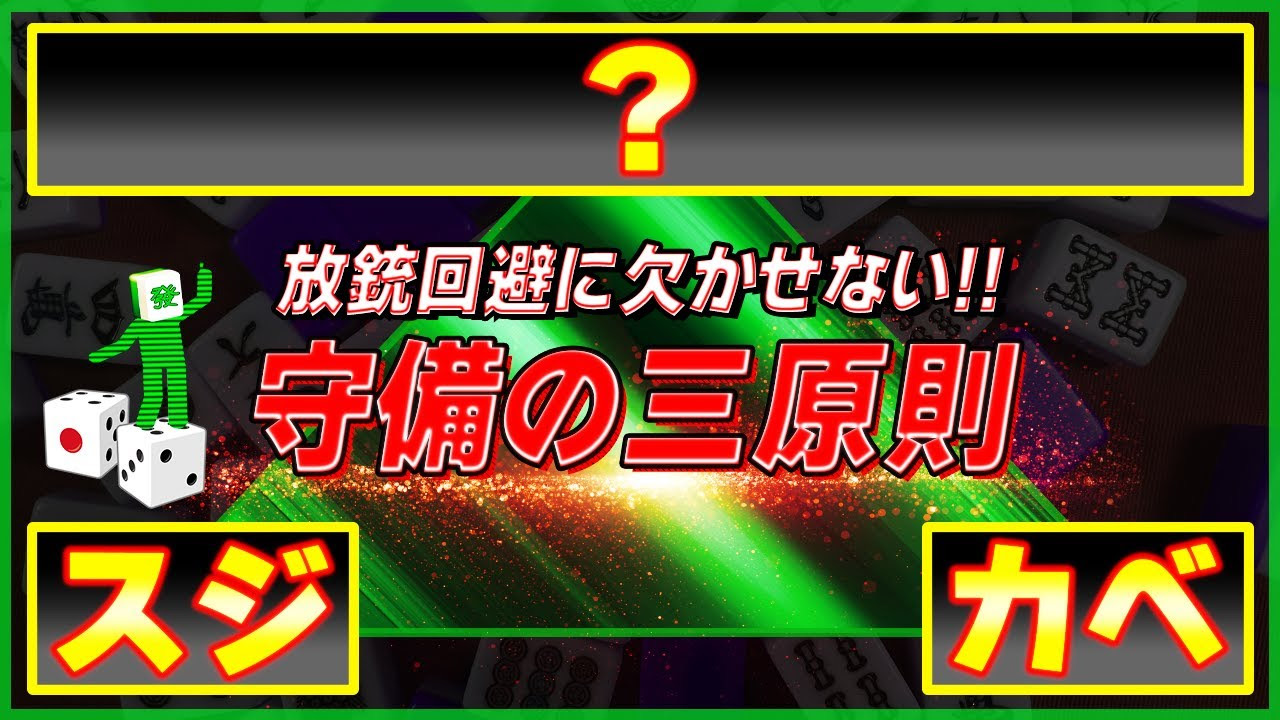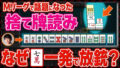麻雀で勝ちたいなら、攻めることと同じくらい、いや、それ以上に「守ること」が重要だ。しかし、相手からのリーチに怯え、何をどう守ればいいのか分からず、結果的に痛い放銃をしてしまった…そんな経験はないだろうか?
もし、麻雀の守備において、絶対に押さえておくべき「三つの原則」があり、それを実践するだけで、あなたの放銃率は劇的に下がり、成績が安定するとしたら、知りたくないだろうか?
YouTubeチャンネル「発男道場」で公開された動画「【麻雀解説】超重要な守備の三原則(初心者向け)」では、まさにその麻雀守備の根幹をなす、初心者必見の「三原則」が徹底解説されている。本記事では、その核心的なポイントを凝縮して紹介しよう。
本記事は発男道場の動画より
麻雀守備の礎となる「三原則」
この動画は、麻雀初心者向けに「守備の三原則」として、守備力を上げるための3つの重要な考え方を解説している。
・筋(スジ)
・壁(カベ)
・序盤に切られている牌の外側は比較的安全
筋と壁に関しては関連動画より
3つ目の原則「序盤の捨て牌の外側」
動画では特に3つ目の原則について詳しく掘り下げている。
- ・なぜ安全か?
例えば、3巡目に「3s」が切られている場合、相手が「334s」の形から「3s」を切って「2s」と「5s」の両面待ちを固定することは考えにくいため、「2s」は比較的安全と判断できる。 - ・注意点(通用しないケース) この原則には例外があり、以下の点に注意が必要。
◯捨て牌が不自然な場合:字牌よりも先に数牌の中張牌が切られているなど、捨て牌の流れが通常と異なる場合。七対子やチャンタなどの特殊な役を狙っている可能性があり、外側の牌が安全とは限らない。
◯ドラが絡む場合:ドラが「8s」の時に、相手が「778s」の形からドラの「8s」を使うために早めに「7s」を切ることがあります。この場合、外側の「9s」は安全ではない。
◯赤ドラが絡む場合:ドラと同様に、赤ドラの「5」を使いたいために、「445(赤)」の形から「4」を早めに切るケースなど。
三原則の併用
動画の最後では、これらの原則を単体で使うのではなく、組み合わせて(併用して)安全な牌を見つけるテクニックも紹介されている。例えば、「壁」と「序盤の捨て牌の外側」の考え方を組み合わせることで、一見安全牌がなさそうな場面でも、より通りやすい牌を推測できる。これらはプロも使う非常に重要な考え方であり、守備の基礎として真っ先に覚えてほしい内容だ。
この三原則を常に意識し、実践するだけで、あなたの守備力は格段に向上し、無駄な放銃は確実に減っていくはずだ。ぜひ動画本編で、具体的な例と共に、これらの原則を深く理解し、あなたの麻雀に鉄壁の守備を取り入れてほしい。